※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
酸化熟成ワインの世界 ― ジュラ、シェリー、そして“酸化香”という個性
■ はじめに:酸化を“コントロールする芸術”
前回の記事では、酸化はワインの“呼吸”だとお話ししました。
今回はその呼吸を意図的に操る造り手たちの物語。
彼らは酸素を恐れず、むしろワインに酸化という時間の表現を与える。
その結果生まれるのが、ヴァン・ジョーヌやシェリーのような、唯一無二の世界です。
■ ジュラのヴァン・ジョーヌ ― 酸化と酵母の静かな共存
フランス東部、スイス国境に近いジュラ地方。
ここでは、ソーヴィニヨン(Savagnin)という白ブドウから造られる
「ヴァン・ジョーヌ(Vin Jaune=黄色いワイン)」が生まれます。
ヴァン・ジョーヌは、樽を満たさずに約6年間熟成されます。
その間、ワインの表面にヴォル(voile)=産膜酵母が自然に形成され、
酸素を遮りながらも、微量な酸化を穏やかに進めます。
結果として、香りは次第に変化していきます。
| 熟成初期 | 中期 | 完熟期 |
|---|---|---|
| 青リンゴ、シトラス | ヘーゼルナッツ、カレーリーフ | クルミ、カラメル、熟チーズ |
この香りを生む主役は、アセトアルデヒド(CH₃CHO)。
酸化によって生成されるこの化合物が、独特のナッツ香やスパイス香を形づくります。
ヴァン・ジョーヌの香りを嗅ぐとき、
「酸化がワインの“時間”を語っている」と実感できるでしょう。
■ スペインのシェリー ― 酸化を設計した文化遺産
スペイン南部アンダルシア地方の**ヘレス(Jerez)**では、
酸化と発酵が共存する“二層構造の熟成”が発展しました。
ここでも酸化は、造り手がコントロールする「設計された現象」です。
🔸 生物学的熟成(フィノ・マンサニージャ)
酵母の膜「フロール」がワイン表面を覆い、酸化を防ぎながら独特の香りを作ります。
アセトアルデヒドの生成が穏やかに進み、ナッツ・ハーブ・パン生地のような香りが現れます。
🔸 酸化的熟成(アモンティリャード・オロロソ)
フロールが消えると、酸化熟成が一気に進みます。
色は琥珀色に、香りはドライフルーツ・キャラメル・タバコへ。
熟成環境の酸素量、樽の種類、補酒(ワインを継ぎ足す頻度)まで計算し尽くされ、
まさに「酸化をデザインする文化」です。
 あお所長
あお所長🌞 関連記事:シェリーはなぜ生まれたのか?
乾いた大地と太陽、イスラムの時代、そして偶然の航海――
シェリーが“酸化を受け入れた”理由を、歴史と文化から読み解く。
👉 シェリーはなぜ生まれたのか ― 酸化と太陽が生んだ、ワイン史上もっとも美しい偶然
■ マデイラ ― 火と酸素が生む“永遠のワイン”
大西洋の孤島・マデイラ島では、
ワインを意図的に加熱・酸化熟成させます。
18世紀、船旅の途中で熱を受けて味が変わったのを再現したのが始まり。
高温下で酸化が進み、キャラメル、焼きナッツ、コーヒー、蜜のような香りを得ます。
マデイラは「酸化しても崩れないワイン」。
むしろ酸化こそが、彼らのアイデンティティなのです。
■ 酸化香は欠陥ではない ― “風味の文法”としての酸化
酸化香(oxidative note)は、ワインの欠点ではなく“言語”です。
その発生量とバランスを操ることで、造り手はワインに物語を刻みます。
| 酸化レベル | 香りの印象 | 感じ方 |
|---|---|---|
| 微酸化 | まろやか、旨味の増加 | 熟成感・深み |
| 中程度 | ナッツ・ハーブ・蜂蜜 | 酸化スタイル |
| 強酸化 | 酢酸・カラメル | 酸化臭(欠陥) |
「酸化=悪」ではなく、「酸化をどう使うか」が造り手の哲学。
酸化の設計とは、香りと熟成の設計なのです。



🧪 関連記事:酸化のメカニズムを科学で理解する
シェリーやヴァン・ジョーヌの香りを作るのは、
実は酸化と還元の“電子のやり取り”です。
ワイン中で何が起こっているのか、フェノールやSO₂の働きを詳しく解説しています。
👉 ワインの酸化、怖くない。香りと熟成を変える「見えない反応」の正体
👓 所長あおのひとこと
「酸化を“理解して”から飲むと、ヴァン・ジョーヌの香りが全く違って感じますよ。」
■ 酸化スタイルと料理のペアリング
酸化香をもつワインは、火を通した料理・熟成食材と抜群の相性を見せます。
| ワイン | 香り | 相性料理 |
|---|---|---|
| ヴァン・ジョーヌ(ジュラ) | クルミ、カレー、チーズ | モリーユ茸のクリーム煮、コンテチーズ |
| アモンティリャード(シェリー) | ナッツ、ドライフルーツ | ローストポーク、アヒージョ |
| マデイラ | 蜂蜜、キャラメル、スパイス | フォアグラ、ショコラ、焼きナッツ |
🍽️ 火を通した旨味と酸化香の“焦がしトーン”が響き合う。
フレッシュさではなく、「余韻と温度」でペアリングするのがコツ。
■ 結論:酸化は「熟成と個性のデザイン」
ジュラ、シェリー、マデイラに共通するのは、
酸化を“敵”ではなく“表現の手段”として扱っていること。
造り手は酸素を味方につけ、
時間の中で香りを育て、個性を際立たせる。
次回(シリーズ③)では、逆に酸化が行きすぎたときの“オフフレーバー”――
酸化臭・揮発酸・メタリック香などを科学的に見ていきます。
🍷 酸化はワインの「言葉」。
その語彙を増やすことが、ソムリエの感性を豊かにします。
🍷 酸化シリーズを順に読む
| 回 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 🧪 第1弾:酸化の科学篇 | 酸化のメカニズムを解説。フェノール・SO₂・金属の役割を理解する。 | |
| 🍇 第2弾:酸化熟成ワイン篇(現在地) | ジュラ、シェリー、マデイラ――酸化を文化として昇華させた造り手たち。 | |
| ⚗️ 第3弾:オフフレーバー篇 | 酸化が行きすぎたときに現れる「酸化臭・揮発酸・金属香」を科学で嗅ぎ分ける。 |
💬 次の記事では「酸化の裏側」――
ワインが“疲れてしまう瞬間”の化学を解き明かします。
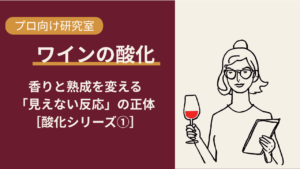
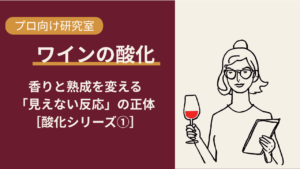




※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクからお申込みいただいた場合、当サイトに報酬が発生することがあります。ただし、紹介しているスクールは私自身が実際に受講し、心からおすすめできるものだけを掲載しています。
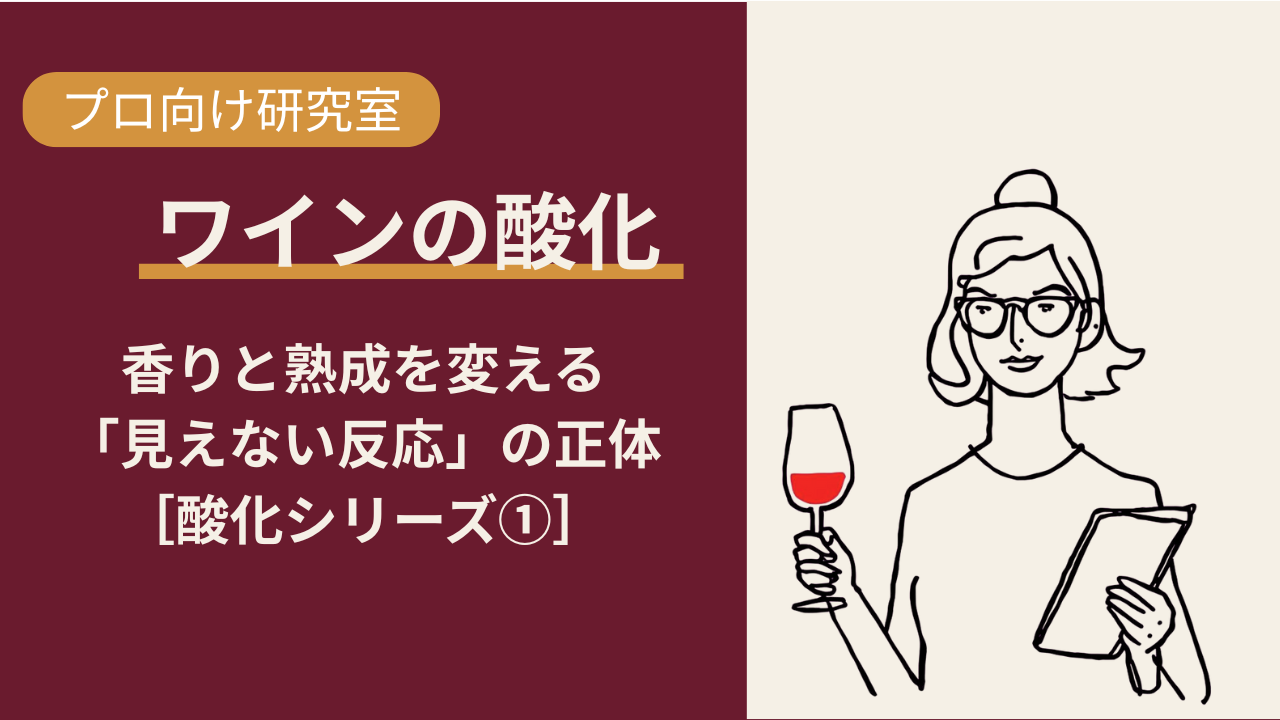

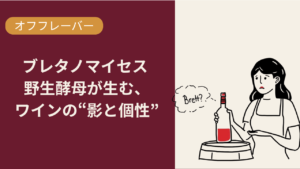
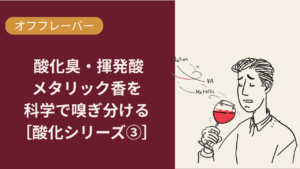
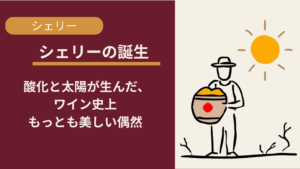
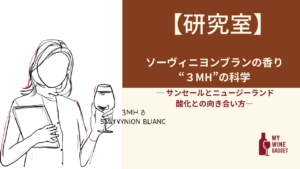
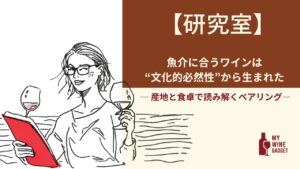
コメント