※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
🧭 はじめに:ワインに潜む「野生の声」
「このワイン、ちょっと動物っぽいですね。」
そう評されるワインの多くには、**ブレタノマイセス(Brettanomyces)**という野生酵母が関わっています。
一見すると個性的で魅力的。
しかし同時に、それは果実香を壊し、産地の個性を覆い隠すリスクでもあります。
「ブレタノマイセスは、ワインに野生を与えるが、個性を奪うこともある。」
■ 1. Brettanomycesとは何者か
Brettは、ワイン中に自然発生する野生酵母の一種です。
学名:Brettanomyces bruxellensis。
低酸素でも増殖でき、SO₂が少ない環境で活性化します。
古樽やワイナリーの壁面など、清掃しきれない箇所に潜むことが多く、
制御が難しいため「ワイナリーの亡霊」と呼ばれることも。
Brettは“自然”ではなく、“管理不備”のサインでもある。
■ 2. 香りの正体 ― 馬小屋、革、そして果実を覆う影
Brettが発生すると、4-エチルフェノールや4-エチルグアイアコールという揮発性フェノールを生成します。
| 化合物 | 香り | 影響 |
|---|---|---|
| 4-EP | 馬小屋、革、湿った木 | 果実香をマスクする |
| 4-EG | スモーク、クローブ | 適量で複雑さ、過剰で焦げ臭 |
これらは、ナチュラルワイン愛好家の間では「ワイルド」「オールドスクール」とも言われますが、
果実の透明感・品種特性・産地の違いを消してしまう傾向があります。
🍇 ブルゴーニュのピノ・ノワールがどの畑でも同じ“獣臭”になる――
それがBrett汚染の怖さです。
■ 3. 酸化との関係 ― 酵母が侵入する“隙”
Brettは、酸化によってSO₂が枯渇したタイミングで活動を始めます。
つまり、酸化管理の不備が彼らの活動を呼び込む。
| 条件 | Brettの動き |
|---|---|
| SO₂不足 | 活動開始 |
| 微酸素環境 | 増殖しやすい |
| 古樽使用 | 定着・再感染リスク |
| 高pH(>3.6) | 酸抵抗性が上昇 |
🧪 Brettは“自然発生”ではない。
それは「管理された酸化」が破綻したときの結果なのです。
■ 4. ナチュラルワインにおけるBrettの誤解
ナチュラルワインの世界では、Brettが“自然の味わい”として語られることがあります。
しかし、多くの醸造学者やソムリエは警鐘を鳴らしています。
🔻 よくある誤解と実際
| よくある主張 | 実際のリスク |
|---|---|
| 「Brettは自然酵母だから良い」 | Brettは制御不能。再発酵・酸化・揮発酸の原因になる。 |
| 「ナチュラルの証拠」 | Brett臭は生産者の哲学ではなく衛生・酸化管理の問題。 |
| 「複雑さの源」 | 果実香とテロワールをマスク。全てを“同じ臭い”にする。 |
👓 所長コメント
「“ナチュラル”を掲げるなら、Brettに頼らずに自然を表現してほしいですね。野生と汚染は、似て非なるものですだと思いませんか。」
■ 5. 世界の評価分裂 ― 容認と拒絶のあいだで
| 立場 | Brettへの評価 | 主な地域・思想 |
|---|---|---|
| 否定派(科学主義) | 果実・テロワールの破壊。除去すべき汚染。 | ニューワールド、醸造学者 |
| 中庸派(伝統派) | 微量なら熟成の一部として許容。 | ボルドー、ローヌ、ブルゴーニュ古酒 |
| 容認派(自然派) | Brettも自然の一部として受け入れる。 | ジュラ、ロワール、自然派造り手 |
いずれにしても、“意図的に使う”か“放置する”かの違いは大きい。
本質的なナチュラル哲学とは、「放任」ではなく「非介入的な設計」なのです。
■ 6. 防御と再発 ― 醸造現場が恐れる理由
ブレタノマイセスは、一度感染すると完全除去が難しい。
SO₂、清潔な器具、温度管理――その全てが防御の基本です。
| 状況 | 予防・対応策 |
|---|---|
| 樽内感染 | 熱湯・スチーム・オゾン洗浄 |
| 微酸化環境 | 密閉・窒素置換 |
| 瓶内二次汚染 | 滅菌ろ過 or 滴定SO₂ 20mg/L以上維持 |
| 計測 | Brett DNA検出(PCR法) |
Brettの制御に失敗すると、
「汚染ワイナリー」としてラベルを貼られ、市場から信頼を失うリスクもあります。
■ 7. 結論 ― “野性”を愛するには、まず制御を学べ
Brettは、自然の美しさと残酷さの両方を映します。
問題は、それを“理解せずに放置すること”。
🍷 真のナチュラルは、放任ではなく意識的な静観。
Brettを理解し、許容し、制御しないといけません。
そこに、職人の哲学が宿ると思います。
🍷 関連記事でさらに学ぶ
- 🧪 酸化の科学篇
酸素がワインをどう変えるのか? 酸化の仕組みを科学で解説。 - 🍇 酸化熟成ワイン篇
ジュラやシェリー、酸化を芸術に変えた造り手たち。 - ⚗️ オフフレーバー篇
酸化臭・揮発酸・金属香。酸化の“崩壊”を嗅ぎ分ける。



※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクからお申込みいただいた場合、当サイトに報酬が発生することがあります。ただし、紹介しているスクールは私自身が実際に受講し、心からおすすめできるものだけを掲載しています。
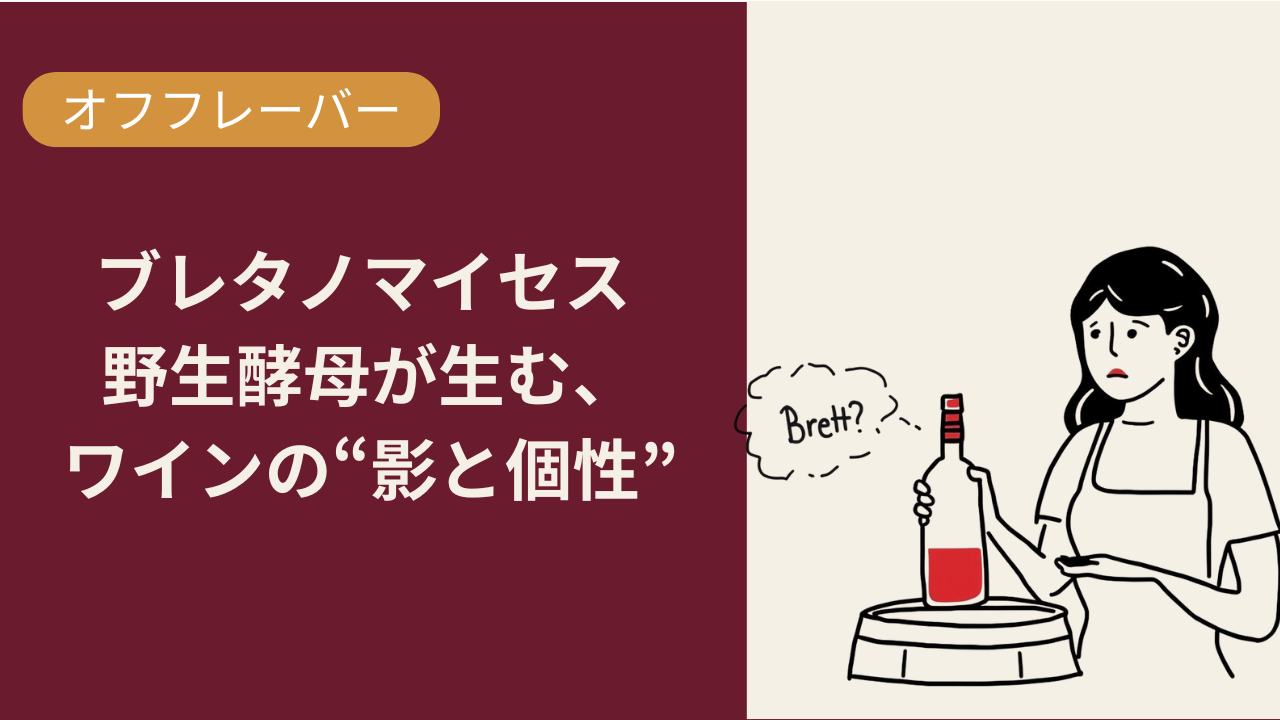


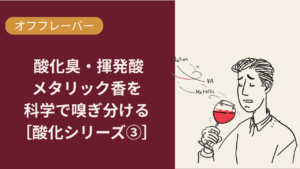
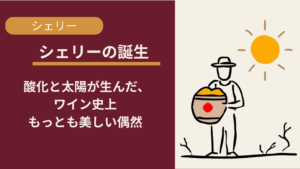
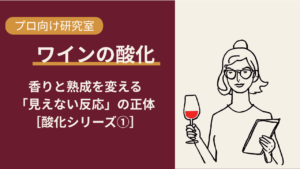
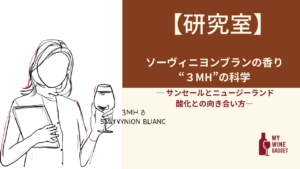
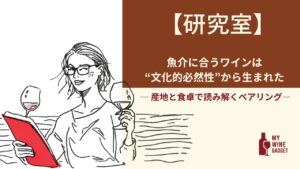

コメント