🍷 ワイングラスの形で香りと味わいはどう変わる?
ワインを注いだ瞬間、立ちのぼる香りが「今日は違うな」と感じることがあります。
温度でもなく、銘柄でもなく、グラスの形が違うだけで、
まるで別のワインを飲んでいるように感じられることも。
「香りが先か、味が先か」——
そんな疑問を確かめたくて、同じワインを形の異なるグラスに注ぎ、
静かに観察してみました。
🧪 実験条件:グラスを変えて、同じワインで比較
使用したのは3種類のグラスです。
| グラス | 特徴 | 形のポイント |
|---|---|---|
| ボルドー型 | 背が高く、口径がやや広い | 香りと空気がよく混ざる |
| ブルゴーニュ型 | 丸く広がるボウル | 香りをため込みやすい |
| 白ワイン型 | 小ぶりで口径が狭い | 香りが集中しやすい |
ワインは1本に統一。
15℃で注ぎ、香りと味わいをそれぞれ15分ほど観察しました。
🌬️ 香りの“広がり”は空気の地図
まず驚いたのは、香りの「方向」が違うということ。
- ボルドー型では、香りがすぐに立ち上がり、
フルーツのような甘い香りが先に広がりました。 - ブルゴーニュ型は、香りがボウルの中に留まり、
少し時間が経ってから柔らかく花のように広がる。 - 白ワイン型は、香りがピンポイントに上がってきて、
酸やミネラルの輪郭がはっきりします。
 副所長しろ
副所長しろ香りは、空気の中をどう流れるかで印象が変わる。
グラスの形は、その流れを設計する地図のようなものです。
👅 味わいは“香りの時間差”で変化する
香りが広がる速さが違うと、味わいにも影響が出ます。
同じワインなのに、飲み口が変わるのです。
- ボルドー型:香りが先に開き、果実味がふくらむ。
舌の奥で丸く感じる。 - ブルゴーニュ型:香りが遅れて追いかけてきて、
味の余韻が長く続く。 - 白ワイン型:香りが集中し、酸がシャープに届く。
味わいが引き締まって感じられる。



舌が感じているのは、実は“香りの時間差”なんです。
グラスの形が、味の順番を変えてしまう。
🧭 副所長しろの考察:香りと味わいは“構造の両面”
香りと味わいは、別々に存在しているわけではありません。
香りの流れが変わると、舌に届く風のような空気が変わり、
それが味の印象になる。
だから、グラスの形を変えることは、
香りの“流体構造”を変える行為なんです。
同じワインでも、形が変われば違う物語を語り始める。
それが、ワイングラスの面白さだと思います。
🍇 副所長しろのおすすめ:形の違いを体験する
「香りと味わいの違いを体験してみたい」という方には、
以下のような“同じコンセプトで比較ができるシリーズ”がおすすめです。
- リーデル テイスティングセット
→ 基本の形がセットになっているので、最初のお試しにはぴったり。
気に入ったグラスがあれば、買い足しても良いですね。 - ツヴィーゼル ヴィヴィッドセンス
→ 赤白兼用ながら、同シリーズ内で異なる形が用意されていて、実用的だと思います。
🧩 まとめ|形を変えると、空気の物語が変わる
グラスの形は、香りの流れと味の順番を変える。
それは、単なるデザインではなく、“香りの構造”の違いなんです。
香りを観察することは、味わいの仕組みを理解すること。
そして何より——
同じワインで違う表情を見つける時間は、とても静かで楽しいものです。🍷
🔗 関連リンク




※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクからお申込みいただいた場合、当サイトに報酬が発生することがあります。
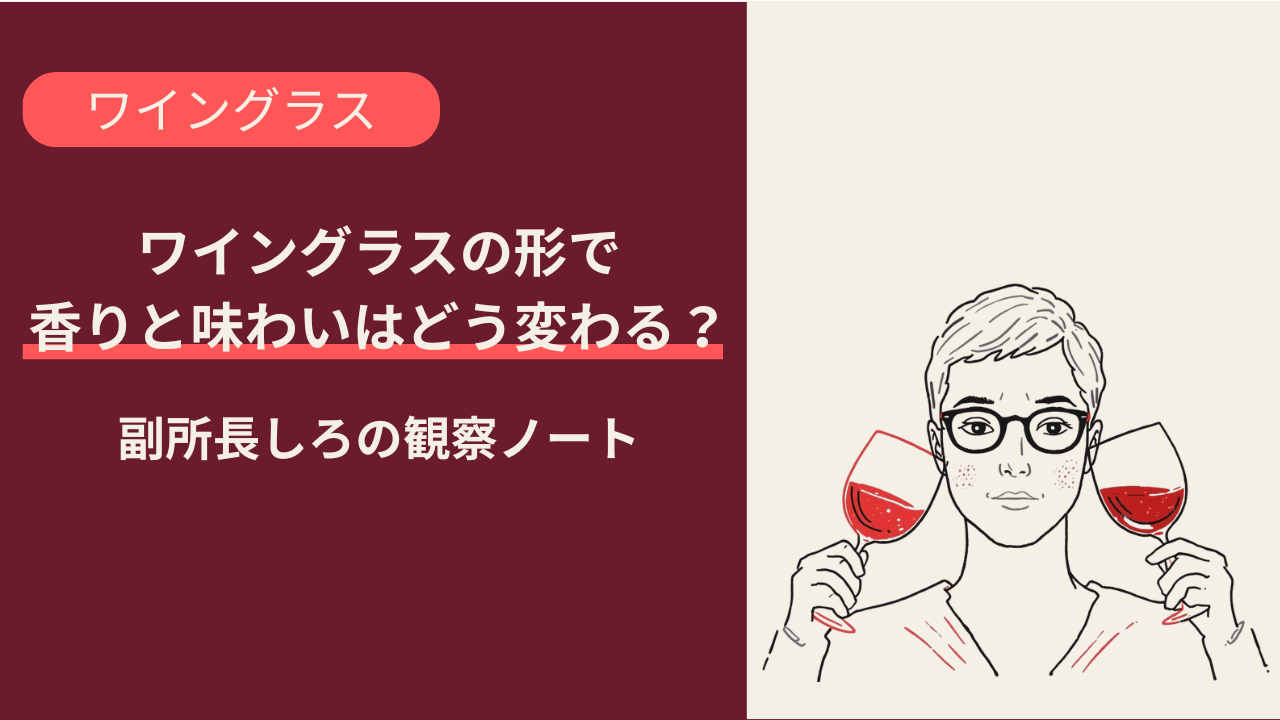
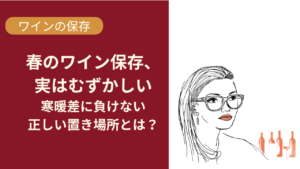
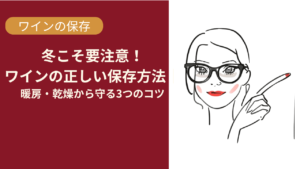
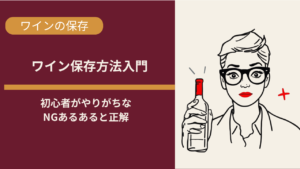

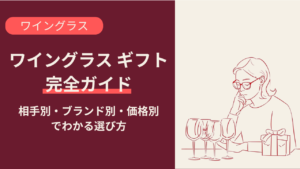

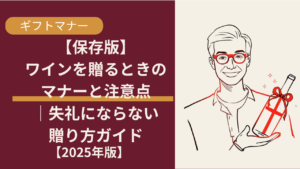
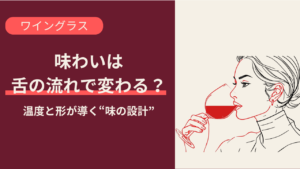
コメント