■ 序章:酸化を「受け入れた」ワイン
ワインの歴史は、酸化との戦いの歴史でもあります。
冷蔵もステンレスもなかった時代、酸化は“劣化”そのものでした。
しかし――
スペイン南部アンダルシアの地では、
誰も想像しなかった「酸化を味方につけるワイン」が誕生します。
その名は シェリー(Sherry)。
世界のどのワインよりも、酸化と向き合い、酸化と共に熟したワインです。

■ 第1章:乾いた大地、燃える太陽 ― 酸化の宿命
舞台は、スペイン南端ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ(Jerez de la Frontera)。
気温40℃、降水量わずか600mm。
アンダルシアの太陽は、ブドウにも人にも容赦がない。
ブドウ畑は白い石灰質土壌「アルバリサ」に覆われ、
光を反射してブドウをさらに焼き上げる。
その結果、果汁は濃く、酸は低く、酸化しやすい。
冷却も酸化防止剤もなかった中世――
この土地で造られたワインは、自然と酸化を受け入れる宿命を背負っていたのです。
■ 第2章:イスラムの時代 ― ワインが「飲み物」ではなかった頃
7世紀から15世紀、アンダルシアはイスラム王朝「アル・アンダルス」の支配下にありました。
イスラム教ではアルコールの飲用が禁じられていたため、
ワインは主に酢や薬用酒、保存液として使われていました。
つまり、酸化しても問題のない「強い酒」が重宝されたのです。
この時代に、酸化に耐える酒質づくりの知恵が育ちました。
ワインは“飲むもの”から、“残すもの”へ。
酸化は、保存のための技術として受け入れられ始めたのです。
■ 第3章:再征服と航海 ― 酸化が「偶然の発見」になる
15世紀後半、レコンキスタ(キリスト教勢力による再征服)が完了し、
アンダルシアは再びヨーロッパのワイン貿易の中心に。
この時代、ヘレスのワインはイギリスやオランダに輸出されました。
しかし船旅は数ヶ月。
灼熱の海上で、ワインは酸素と熱にさらされ続けたのです。
結果、樽の中でワインが褐色に変わり、香りはナッツやキャラメルのように。
当初は“事故”だったその変化が、
ロンドンの商人たちには「驚くほど芳香豊かで複雑」だと絶賛されました。
🍷 劣化が、発見に変わった瞬間。
これが、シェリーの原点です。
■ 第4章:フロールとの出会い ― 酸化と共存する酵母
17〜18世紀。
ある日、ヘレスのボデガ(熟成庫)で不思議な現象が起こります。
樽の表面に、白く薄い膜が自然に張り始めたのです。
それが後に「フロール(flor)」と呼ばれる酵母の膜でした。
この酵母は、酸素を消費しながらアセトアルデヒドを生成し、
ワインを酸化から守る。
つまり――
酸化を防ぎながら、酸化の香りを生むという、矛盾した存在。
酸化と還元の狭間でワインを進化させる“自然のフィルター”
これにより、シェリーは二つの顔を持つようになります。
| スタイル | 熟成タイプ | 香り |
|---|---|---|
| フィノ / マンサニージャ | 生物学的熟成(フロール下) | パン生地、アーモンド、塩味 |
| アモンティリャード / オロロソ | 酸化的熟成(フロール消失後) | ナッツ、カラメル、スパイス |
酵母が守るワイン、酵母が去った後に熟すワイン。
どちらも「酸化と共に生きる」という哲学から生まれたのです。
■ 第5章:ソレラという「時間の装置」
18世紀、シェリーはさらに進化します。
熟成年数の違うワインを少しずつブレンドする「ソレラシステム」。
古いワインの一部を抜き、新しいワインを注ぎ足し、
それを何層にも重ねる――。
この方法により、毎年異なる酸化状態のワインが混ざり、
“時間の平均値”のような味わいが生まれます。
ソレラは、酸化と時間を混ぜ合わせる哲学装置。
そこにあるのは、“永続する熟成”という概念。
■ 結章:酸化を恐れず、酸化と生きる文化
シェリーは、偶然の産物ではありません。
太陽、海風、乾いた空気、そして人間の好奇心――
あらゆる要素が重なり、
酸化を受け入れ、酸化を美に変えたワイン文化が誕生しました。
一方で、同時代の大西洋の島・マデイラでは、
船旅中の“熱劣化”がワインを変え、
「ならば熱を加えよう」と考えた人々がいました。
つまり――
| ワイン | 起源 | 哲学 |
|---|---|---|
| シェリー | 酸化を制御する乾燥の地 | 酸化と共存する文化 |
| マデイラ | 熱で変わる航海ワイン | 酸化を受け入れる文化 |
どちらも、
「自然の不完全さを、文化として完成させたワイン」
です。
■ 余韻:酸化は“時間の物語”
酸化は単なる化学反応ではなく、
土地と人間が交わした契約のようなもの。
シェリーが教えてくれるのは、
「酸化を恐れない勇気」と「時間を信じる哲学」です。
🍷 それは、ワインが酸素と語り合う物語。
そして、私たちが“変化を美しいと思える”ことの証でもあるのです。
■ おまけ:年表
| 時代 | 出来事 | 酸化との関係・文化的背景 |
|---|---|---|
| 紀元前1100年頃 | フェニキア人がアンダルシア沿岸に入植し、初のワイン造りを開始。 | 太陽の強い地で、すでに酸化が避けられない環境。 |
| 紀元前200年頃 | ローマ帝国がイベリア半島を支配。ヘレス周辺でワイン産業が発展。 | 酸化による風味変化が“熟成”として評価されはじめる。 |
| 711年〜1492年 | イスラム王朝(アル・アンダルス)支配。 | 飲用は禁止だが、ワインは酢や薬用液として重宝。酸化を“保存技術”として利用。 |
| 1264年 | カスティーリャ王国がヘレスを奪還。 | キリスト教勢力によりワイン文化復活。酸化熟成の知識が引き継がれる。 |
| 15〜16世紀 | 大航海時代、イギリス・オランダへの輸出開始。 | 船旅でワインが熱・酸素にさらされ、酸化による風味変化が「好ましい偶然」として発見される。 |
| 1561年 | エリザベス1世の時代、シェリーが英国で大流行(“Sack”と呼ばれる)。 | 酸化したワインのナッツ香や厚みが「高級酒」として評価される。 |
| 17世紀後半 | ヘレス地方のボデガでフロール酵母が自然発生。 | 酸化を抑制しつつ酸化香を生む“生物学的熟成”が始まる。 |
| 18世紀 | 「ソレラシステム」が確立。 | 酸化と時間をブレンドして安定した酸化熟成を実現。 |
| 19世紀 | シェリーがヨーロッパ全域に輸出され、王室御用達となる。 | 酸化が芸術的熟成法として定義される。 |
| 20世紀 | 醸造科学の発展で、酸化・還元・アセトアルデヒドの研究が進む。 | 酸化は「制御可能な化学反応」として理解されるようになる。 |
| 現代 | 「ナチュラルワイン」や「酸化熟成」への再評価が進む。 | 造り手は再び、酸化を味わいとしてデザインしはじめている。 |
「偶然の酸化」から「意識的な酸化」へ。
ある意味、シェリーの哲学はナチュラルワインやオレンジワインへと受け継がれているとも言えますね。
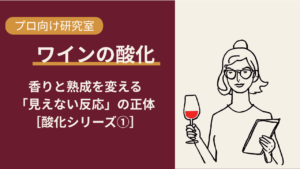
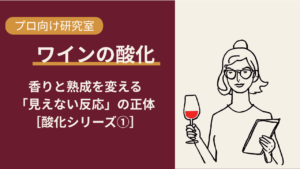

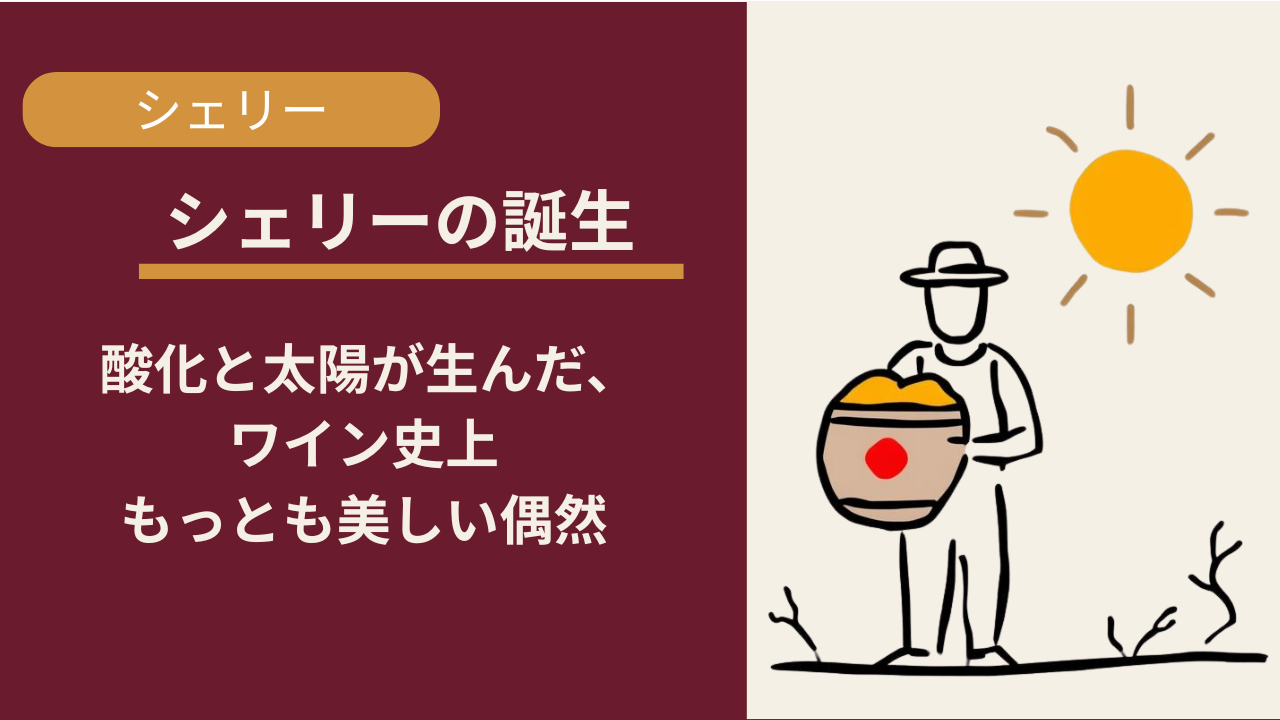


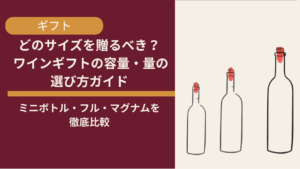
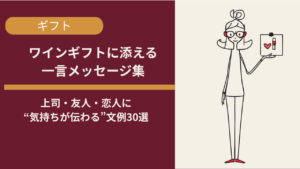
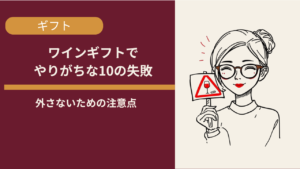
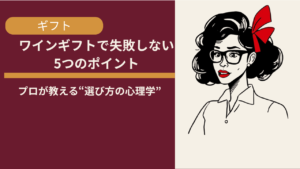

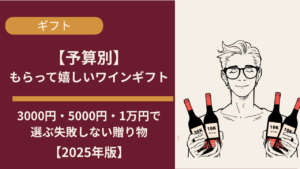
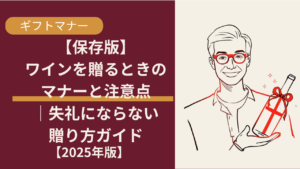
コメント