🍷 味わいは舌の流れで変わる?
同じワインを飲んでも、「今日は少し苦味を感じる」と思うことがあります。
温度も銘柄も同じなのに、印象が違う。
その理由のひとつは、舌の上での流れ方にあります。
ワインが口に入ってから飲み込まれるまでの「動きの経路」が、
味の感じ方を変えているのです。
味わいは、香りや温度の結果ではなく、
舌の中を流れる“経路の設計”によって生まれる現象だと考えています。
👅 味わいをつくる「舌の構造」
舌の表面は均一ではありません。
甘味を感じやすい前方、酸味を感じる側面、苦味を感じる奥——
それぞれが異なる感覚を担当しています。
グラスの形によってワインの流れ方が変わると、
舌のどの部分に最初に触れるかも変化します。
その結果、同じワインでも「甘く感じる」「酸が立つ」といった差が生まれます。
つまり、グラスは香りだけでなく、味の伝わり方まで設計しているのです。
🌡️ 温度が変える“味のバランス”
もうひとつ、味わいに大きく影響するのが温度です。
ワインの温度が低いと、味の成分が穏やかに伝わり、
全体が引き締まって感じられます。
逆に高くなると、酸味や苦味が早く現れ、香りも立ち上がりやすくなります。
これは、温度によってワインの粘度と揮発性が変化するためです。
冷たいと舌の上で流れにくく、温かいと滑らかに広がる。
結果として、味の立ち上がるスピードが異なってくるのです。
 副所長しろ
副所長しろ「温度は、味の“速度”を決める要素。」
同じワインでも、温度が違えば時間の進み方も変わります。
⏳ 舌の上で起こる“時間の変化”
ひと口の中でも、味の印象は刻一刻と変わっています。
最初に甘みを感じ、次に酸味が現れ、
最後に苦味が静かに残る——
この「順番の変化」が、味わいの奥行きをつくっています。
ワインを口に含んで3秒ほど静止し、
ゆっくりと息をしてから飲み込むと、
味の流れと香りの戻りがどのように連動しているかがわかります。



味わいは“瞬間”ではなく“流れ”の中にあります。
その流れをデザインしているのが、グラスの形です。
🍇 副所長しろのおすすめグラス|味の流れを感じる設計
| グラスタイプ | 特徴 | おすすめのワイン |
|---|---|---|
| ボルドータイプ (背が高く、口が広い) | ワインが舌の奥へゆっくり流れ、重心が安定。タンニンの角が丸く感じられる。 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローなど骨格のある赤ワイン |
| ブルゴーニュタイプ (丸みがあり、広がる) | 香りがボウル内に留まり、舌の中央に広く当たる。果実味と酸のバランスが取りやすい。 | ピノ・ノワール、ガメイなど香り重視の赤 |
| 白ワインタイプ (小ぶりで口がすぼまる) | ワインが舌先に当たり、酸が際立つ。温度変化がゆるやかで繊細な味を保てる。 | ソーヴィニヨン・ブラン、リースリングなど |
| ユニヴァーサルタイプ (中間型) | 香りと味の流れがバランスよく設計されており、日常使いに最適。 | ロゼ、ライトボディの赤、フルーティな白 |



グラスは香りだけでなく、舌の流れを設計する道具です。
どんなテンポで味わいたいかを意識すると、自分に合う形が見えてきます。
自分に合うグラスのタイプをもっと詳しく知りたい方は、こちらもどうぞ:
🧭 味わいを設計するとは、“時間の流れを整える”こと
香りは空気の中で変化し、味わいは舌の上で変化します。
その流れの速さや方向を整えるのが、グラスの設計です。
温度、形、そして舌の経路。
それらを少し意識するだけで、ワインの印象は驚くほど変わります。
ぜひあなたのワインにぴったりなグラスを見つけてみてください。
きっと、ワインの世界にハマること間違いなしです。
🔗 関連記事


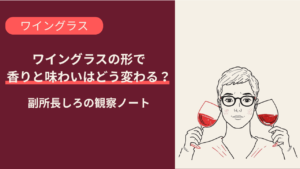
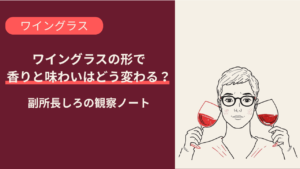


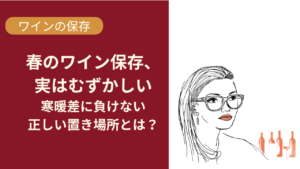
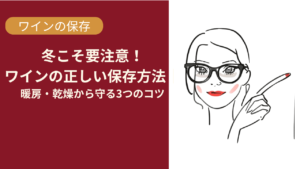
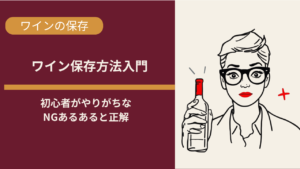

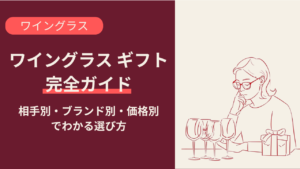

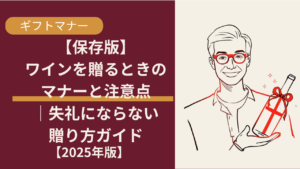
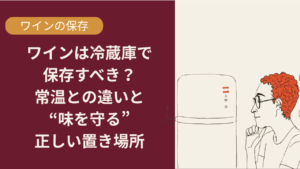
コメント